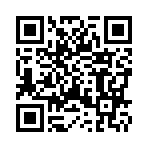2016年05月14日
舛添知事のこと
いろいろ言われているし、舛添氏の言い訳は支離滅裂だけど、1点だけ突っ込ませていただきます。
正月三が日の温泉ホテルへの宿泊について、「事務所関係者らと都知事選挙への対応などを会議した」とし、「家族と宿泊していた部屋を利用した」と言い訳した。
正月三が日に、家族水入らずの宿の部屋で会議したとか、正月三が日に事務所関係者が仕事するかよとか、それはとりあえず置いといて。
ホテルや旅館は普通、宿泊客以外が部屋へ入ることを、宿泊約款とそれに続く利用規則で禁止しています。
「来客と会う際にはロビーでお願いします」とかいう文言を、ホテルなどの部屋の備え付けのファイルに記載されているのを見たことがある人も多いはずです。
舛添氏は、事務所関係者は宿泊していないと明言しています。
だったら、宿泊者以外を部屋に招き入れて会議したと言う舛添氏の行動は、明らかに利用規則違反です。
舛添氏がそういうことを堂々と話すなんて、ホテル側からすれば利用規則違反を理由に宿泊を拒否されてもよい行動なんですよ。天下の東京都知事が、それで良いのですかね。
そういうことに学のある舛添氏は気づいていないし、そういう突っ込みどころに気が付かないマスコミさんも、なんだかなあ~と思った次第です。
まあ、本当に会議したなんて信じている人は、99.9パーセントいないと思いますけどね。
正月三が日の温泉ホテルへの宿泊について、「事務所関係者らと都知事選挙への対応などを会議した」とし、「家族と宿泊していた部屋を利用した」と言い訳した。
正月三が日に、家族水入らずの宿の部屋で会議したとか、正月三が日に事務所関係者が仕事するかよとか、それはとりあえず置いといて。
ホテルや旅館は普通、宿泊客以外が部屋へ入ることを、宿泊約款とそれに続く利用規則で禁止しています。
「来客と会う際にはロビーでお願いします」とかいう文言を、ホテルなどの部屋の備え付けのファイルに記載されているのを見たことがある人も多いはずです。
舛添氏は、事務所関係者は宿泊していないと明言しています。
だったら、宿泊者以外を部屋に招き入れて会議したと言う舛添氏の行動は、明らかに利用規則違反です。
舛添氏がそういうことを堂々と話すなんて、ホテル側からすれば利用規則違反を理由に宿泊を拒否されてもよい行動なんですよ。天下の東京都知事が、それで良いのですかね。
そういうことに学のある舛添氏は気づいていないし、そういう突っ込みどころに気が付かないマスコミさんも、なんだかなあ~と思った次第です。
まあ、本当に会議したなんて信じている人は、99.9パーセントいないと思いますけどね。
2016年05月07日
米原駅周辺散歩 旧線トンネル探索
私の大好きな米原駅。
まだ寒い2月のとある日、周辺を散歩しました。

新幹線に沿って設置されているスプリンクラーへ水を送るポンプ室です。

道路をまたぐ、太い送水管。

このポンプ室の名称です。

スプリンクラー本体。こうやってまじまじと間近で見ること機会もあまりありません。

ヤンマー研究所に設置されている温度計。
新幹線通勤のときはこれで必ず、行き帰りに気温をチェックしていました。

新幹線と東海道本線との交差地点。


真横をEF210が通過。迫力です。いい音だあ。



偶然、ドクターイエローが通過。

京浜東北線のパンタグラフが吹き飛んだ事故で話題となった、セクションの表示。
これは、4両編成ならここを先頭が通過したら、最後尾、要するに全編成がセクションを通過したということ。

同じく、6両、8両、10両と続く。

一番左が、最長編成がクリアした表示。もちろん電車の話しですよ。
貨物とか機関車牽引車は機関車が通過すればOK。

新幹線からいつも見ていた看板。

米原駅の駅弁屋さんの井筒屋。

国鉄時代からある、JRの建物。

滋賀県名物、「とびだし坊や」。いろいろなバージョンがありますが、これが基本形の坊や。

これは車窓から撮ったもの。
廃止された旧線のトンネルを撮ることができました。
未だに放置され、現存しているのです。
あやうく架線柱に被るところでした。

トリミングしてアップにしてみました。
実はこの、米原-彦根間にある現在線への付け替え前の、旧線トンネル坑口に行ってみようと思い立ち、米原駅から歩いたのです。
以前、車窓からちらっと見えたことがあったので。
結局、米原方からは徒歩では行けませんでした。一番、草や葉っぱが少ない時期を選んだのですが。
目の前の山の周囲は道はまったくなく、山へ入ったら草やら木やら倒木がたくさんで、人が歩いた跡のような道筋もなく、手入れされていない山でした。
山越えしてたどり着くにはたぶん1日がかりとなるでしょう。そこまでの準備も心構えもありません。
線路脇を歩けば楽に行けそうだけど、線路のすぐ脇に余裕はなく、あきらかに線路ぎりぎりのJR敷地内を歩くことになるでしょう。
10分間隔くらいで223系とかが120キロで疾走する脇は、はっきり言って危ないし、昨今、写真マニアが線路に立ち入ったとか、よくニュースになるので、新聞に載りたくはないので線路脇を歩くのはやめました。
昔は、幹線でも、線路脇ギリギリを歩いたり横断したりして、撮影場所を探したものです。列車が来たときに気をつけておけば、何も言われなかったものですが・・・。
このトンネル、草木が生い茂る時期は、車窓から確認するのは難しいと思います。
まだ寒い2月のとある日、周辺を散歩しました。
新幹線に沿って設置されているスプリンクラーへ水を送るポンプ室です。
道路をまたぐ、太い送水管。
このポンプ室の名称です。
スプリンクラー本体。こうやってまじまじと間近で見ること機会もあまりありません。
ヤンマー研究所に設置されている温度計。
新幹線通勤のときはこれで必ず、行き帰りに気温をチェックしていました。
新幹線と東海道本線との交差地点。
真横をEF210が通過。迫力です。いい音だあ。
偶然、ドクターイエローが通過。
京浜東北線のパンタグラフが吹き飛んだ事故で話題となった、セクションの表示。
これは、4両編成ならここを先頭が通過したら、最後尾、要するに全編成がセクションを通過したということ。
同じく、6両、8両、10両と続く。
一番左が、最長編成がクリアした表示。もちろん電車の話しですよ。
貨物とか機関車牽引車は機関車が通過すればOK。
新幹線からいつも見ていた看板。
米原駅の駅弁屋さんの井筒屋。
国鉄時代からある、JRの建物。
滋賀県名物、「とびだし坊や」。いろいろなバージョンがありますが、これが基本形の坊や。
これは車窓から撮ったもの。
廃止された旧線のトンネルを撮ることができました。
未だに放置され、現存しているのです。
あやうく架線柱に被るところでした。
トリミングしてアップにしてみました。
実はこの、米原-彦根間にある現在線への付け替え前の、旧線トンネル坑口に行ってみようと思い立ち、米原駅から歩いたのです。
以前、車窓からちらっと見えたことがあったので。
結局、米原方からは徒歩では行けませんでした。一番、草や葉っぱが少ない時期を選んだのですが。
目の前の山の周囲は道はまったくなく、山へ入ったら草やら木やら倒木がたくさんで、人が歩いた跡のような道筋もなく、手入れされていない山でした。
山越えしてたどり着くにはたぶん1日がかりとなるでしょう。そこまでの準備も心構えもありません。
線路脇を歩けば楽に行けそうだけど、線路のすぐ脇に余裕はなく、あきらかに線路ぎりぎりのJR敷地内を歩くことになるでしょう。
10分間隔くらいで223系とかが120キロで疾走する脇は、はっきり言って危ないし、昨今、写真マニアが線路に立ち入ったとか、よくニュースになるので、新聞に載りたくはないので線路脇を歩くのはやめました。
昔は、幹線でも、線路脇ギリギリを歩いたり横断したりして、撮影場所を探したものです。列車が来たときに気をつけておけば、何も言われなかったものですが・・・。
このトンネル、草木が生い茂る時期は、車窓から確認するのは難しいと思います。
2016年05月07日
安土駅跨線橋
東海道本線の安土駅にある古い跨線橋が、以前から気になっていました。
近々、安土駅が改修されるようなうわさが聞こえてきたので、3月に訪問しました。
駅員さんに聞くと、古い跨線橋は取り壊され仮設跨線橋になるが、いま作っている新跨線橋も仮設で、最終的な形になるまでの設置とのこと。
新駅舎は今はやりの橋上駅舎となり、どこにでもある形になるみたいです。


キオスクは営業しているようだけれど、閉まっていました。


典型的な国鉄型小駅タイプの駅舎内と改札口。

これがその跨線橋。現役なのもあとわずかのようです。


ホーム上屋も、古レールの柱のレトロなもの。

上屋の財産標識では、昭和38年9月製。私の誕生年月といっしょ。

内部です。





木枠の窓とカギ。昭和を感じます。
古い跨線橋でも、アルミサッシに取り換えてあるところも多いですが、ここは片側だけオリジナルのままです。


工事の案内。

古跨線橋から米原方を見る。

これが建設中の仮跨線橋。
4月になって、仮跨線橋の運用が始まり、古跨線橋は出入り口に蓋をされて、立ち入られなくなりました。
これから安土駅は激変することでしょう。
近接の篠原駅や稲枝駅、河瀬駅も、ここ数年で改修されてきました。
篠原駅なんか、車窓から見ると良い雰囲気だったのになあ。
まあ、橋上化で通り抜けできたりと便利になるのだけど、歴史的建造物を活用はできないものでしょうか。
近々、安土駅が改修されるようなうわさが聞こえてきたので、3月に訪問しました。
駅員さんに聞くと、古い跨線橋は取り壊され仮設跨線橋になるが、いま作っている新跨線橋も仮設で、最終的な形になるまでの設置とのこと。
新駅舎は今はやりの橋上駅舎となり、どこにでもある形になるみたいです。
キオスクは営業しているようだけれど、閉まっていました。
典型的な国鉄型小駅タイプの駅舎内と改札口。
これがその跨線橋。現役なのもあとわずかのようです。
ホーム上屋も、古レールの柱のレトロなもの。
上屋の財産標識では、昭和38年9月製。私の誕生年月といっしょ。
内部です。
木枠の窓とカギ。昭和を感じます。
古い跨線橋でも、アルミサッシに取り換えてあるところも多いですが、ここは片側だけオリジナルのままです。
工事の案内。
古跨線橋から米原方を見る。
これが建設中の仮跨線橋。
4月になって、仮跨線橋の運用が始まり、古跨線橋は出入り口に蓋をされて、立ち入られなくなりました。
これから安土駅は激変することでしょう。
近接の篠原駅や稲枝駅、河瀬駅も、ここ数年で改修されてきました。
篠原駅なんか、車窓から見ると良い雰囲気だったのになあ。
まあ、橋上化で通り抜けできたりと便利になるのだけど、歴史的建造物を活用はできないものでしょうか。